住宅設計の打合せで、設計事務所や建築家から「壁クロスは柄を入れすぎないほうが良い」と言われることがあります。なぜでしょう?結論はシンプルで、建築は“長く使う器(うつわ)”だから。今回は、後悔しない内装計画の考え方を建築家の視点で解説します。
やっぱりクロスに柄を入れたい!…その前に
「花柄を使いたい」「コンクリート柄にしたい」「原色クロスで個性を出したい」。どれも間違いではありません。ただし“面積×期間”のインパクトが大きいのが“壁”。空間の大部分を占め、しかも10〜20年単位で視界にあり続けます。だからこそ、設計段階では慎重に判断したいのです。
建築は「白いキャンバス」。家具と照明で色を足す
絵を描く時の紙は白が基本。住まいも同じで、ベースはニュートラルに整え、可変性の高い要素(家具・雑貨・照明)で色や柄を足すのがセオリーです。流行や趣味は変わります。建物そのものに強い主張を入れるほど、後で“模様替え”が効かなくなります。
色や柄は「動かせるもの」へ
アクセントは家具・アート・ラグ・カーテン・観葉植物などで。家具の入れ替えやレイアウト変更で気分転換ができます。持ち物との相性は持ち込み家具の考え方も参考に。
照明計画で“雰囲気の柄”をつくる
光の当て方や器具のテクスチャで、壁面に陰影や表情(“光の柄”)をつくれます。器具を替えるだけで雰囲気が変わるため、コスト効率と可変性が高いのが利点です。夜の居心地は吹抜けの採光計画や、通風・換気とのセットで整えると効果的。
「飽きない背景」をつくる3つのコツ
- ベースは白〜淡色+マット:反射を抑え、家具の色が映える。
- アクセントは小面積に限定:ニッチ1面やトイレ背面など“引き”で効かせる。
- 素材の質感で差をつける:塗装/クロスでもテクスチャを選べば上質に。
どうしても柄クロスを使うなら、面積・場所・照度を絞るのがコツ。貼替えのしやすい小空間(トイレ・WIC・書斎)に限定すれば、将来の模様替えも容易です。
設計で“長く似合う家”にする
建物の価値はプラン・性能・光の取り回しで決まります。ベースを普遍的に整えておけば、家具や雑貨でいくらでも表情を変えられます。詳しくは家づくりハウツーや、依頼先の選び方もあわせてご覧ください。
まとめ
壁は白いキャンバス。大面積の柄や強い色は後戻りが難しく、流行の影響も受けやすいもの。まずは普遍性の高い背景をつくり、色や柄は“動かせる要素”で楽しむ。それが、長く心地よく暮らすインテリア計画の近道です。
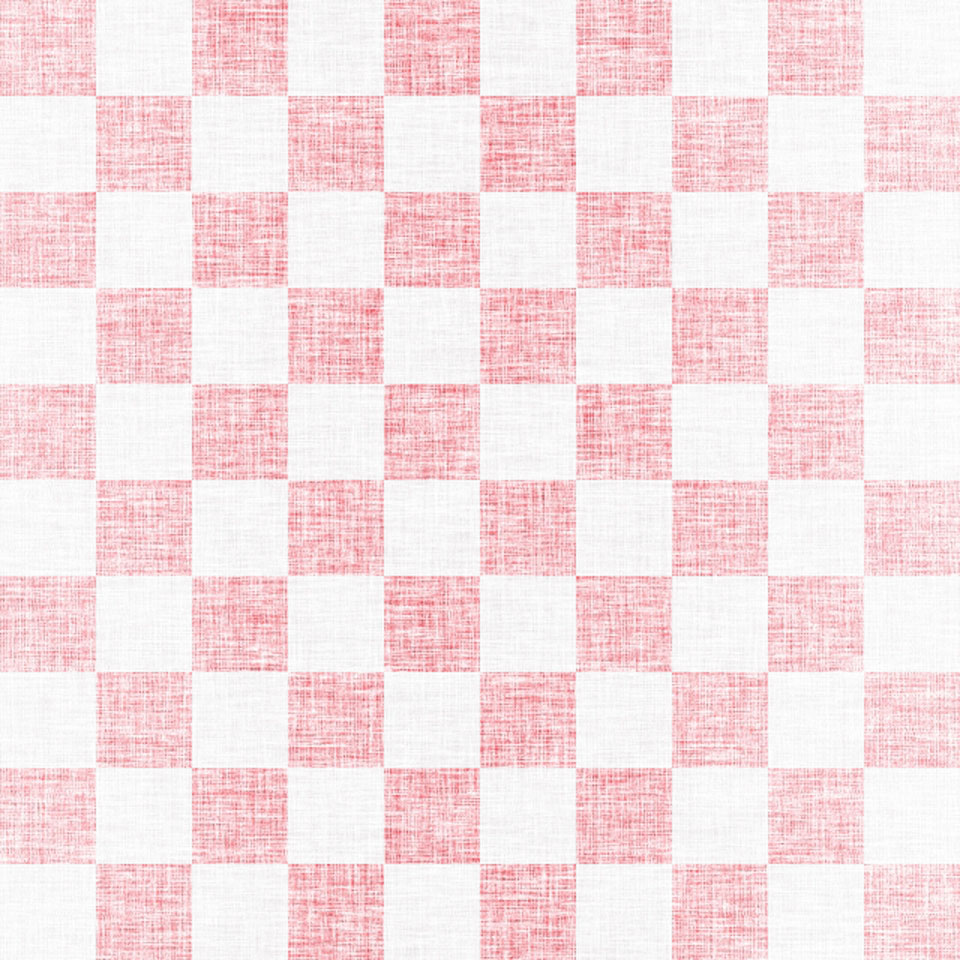






コメント