狭小敷地では間取りがある程度パターン化しやすく、例えば次のような構成が一般的です:
駐車スペースを確保する場合には、水回りを2階以上に持ち上げるケースもあります。
限られた空間を最大限に活かすためには、建築家による住宅設計の工夫が欠かせません。
建築規制と斜線制限
都市部の狭小地では建築基準法による斜線制限が大きな影響を与えます。代表的なものには以下があります:
特に北側斜線や高度斜線は建物の外観や屋根形状に強い制約を与えるため、設計段階でしっかりと検討する必要があります。
まとめ:狭小地でこそ建築家の力を活かす
狭小地で住宅を建てる際には、駐車計画・階数・間取り・建築規制など複数の制約を考慮する必要があります。
ただし、それらを逆手に取れば特徴的で個性的なデザイン住宅を実現できるチャンスにもなります。
敷地条件をどう活かすかは設計次第です。ぜひ失敗しない家づくりのためにも、経験豊富な東京事務所や香川事務所へご相談ください。
この記事を読まれている方の中には、狭小地に住宅を計画しようとしている方も多いのではないでしょうか?今回は狭小地における設計で気を付けるべきポイントを建築家の視点から解説していきます。
狭小地・狭小住宅の設計ポイント
郊外ではあまり馴染みがありませんが、都心部で住宅を建てる場合は狭小地に当たるケースが多くあります。
制約が多い反面、建築家にとっては設計力を発揮できる舞台でもあります。
駐車スペースの確保
狭小地でまず大きな課題となるのが駐車スペースです。横付けで1台確保するケースもあれば、インナーガレージにして建物と一体的に計画する場合もあります。
ただしインナーガレージにすると1階部分がほぼ駐車場になるため、居住空間は2階以上が中心になります。

生活スタイルによっては月極駐車場の利用を視野に入れるのも一つの選択肢です。将来的に車を利用するかどうかを考えておくことも重要です。
階数と生活スタイルの関係
狭小住宅では3階建て以上になる可能性が高いです。そのため、若い時には問題がなくても、将来的に階段の昇り降りが負担になることを想定しておく必要があります。
3階部分を子供室とするなど、ライフステージに合わせた活用方法を事前に考えておくと安心です。

間取りの制約と工夫
狭小敷地では間取りがある程度パターン化しやすく、例えば次のような構成が一般的です:
駐車スペースを確保する場合には、水回りを2階以上に持ち上げるケースもあります。
限られた空間を最大限に活かすためには、建築家による住宅設計の工夫が欠かせません。

建築規制と斜線制限
都市部の狭小地では建築基準法による斜線制限が大きな影響を与えます。代表的なものには以下があります:
特に北側斜線や高度斜線は建物の外観や屋根形状に強い制約を与えるため、設計段階でしっかりと検討する必要があります。
まとめ:狭小地でこそ建築家の力を活かす
狭小地で住宅を建てる際には、駐車計画・階数・間取り・建築規制など複数の制約を考慮する必要があります。
ただし、それらを逆手に取れば特徴的で個性的なデザイン住宅を実現できるチャンスにもなります。
敷地条件をどう活かすかは設計次第です。ぜひ失敗しない家づくりのためにも、経験豊富な東京事務所や香川事務所へご相談ください。






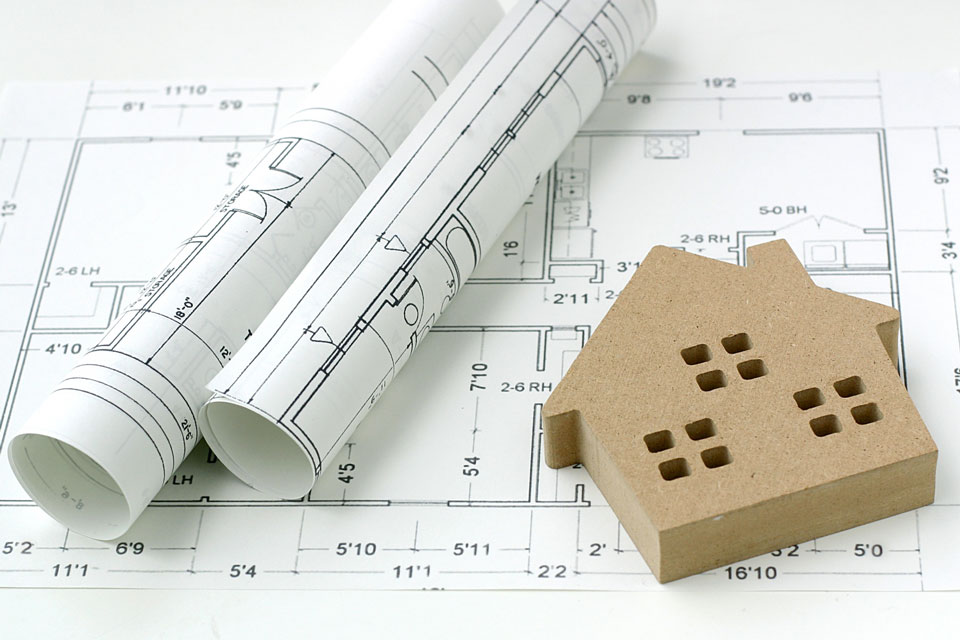
コメント