バリアフリーの考え方は、住宅のような個人や家族レベルから都市のような公共レベルまで幅広く使われています。今回は、住宅におけるバリアフリーについて、建築家の視点からわかりやすく解説します。
バリアフリーとは?
バリアフリーとは、高齢者や障害者など社会的弱者が生活する上で支障となる物理的・心理的な障壁を取り除く考え方を指します。住宅設計においては「安全性」「快適性」「将来への備え」が重要なポイントです。
住宅におけるバリアフリーとは?
住宅の場所や部位ごとにどのような工夫をすれば良いのか、具体例を見ていきましょう。
玄関
車いすが通れる有効幅75cm以上の扉を確保し、段差をなくすことが大切です。最近は玄関ポーチからスロープを設ける設計も増えており、性能とデザインの両立が重視されています。
床(共通)
高齢者にとって最も大きな障害が床の段差です。段差をなくすことで転倒リスクを軽減できます。リフォームの場合でも失敗しない家づくりの一環として検討することをおすすめします。
浴室
浴槽の立ち上がりを40cm以下に抑え、手すりを設置することで入浴動作を安全にサポート。出入口の段差もなくし、ヒートショック対策と合わせた空間設計が望まれます。
便所
立ち座りの負担を減らすために洋式便器を採用し、手すりを配置します。浴室と同様、出入口の段差をなくすことが重要です。
照明
間接照明や反射率の低い内装材を使うことで、まぶしさ(不快グレア)を軽減。視覚的なストレスを減らし、安全性を高めます。
スイッチ・コンセント
床から40〜100cmの高さに設置することで、屈む動作を減らし利用者の負担を軽減。スイッチはワイドタイプを採用するのがおすすめです。
まとめ
バリアフリー住宅は、新築時だけでなくリノベーションでも計画可能です。手すりの下地を事前に入れておくなど将来対応できる設計を行うことが重要です。詳しくは建築ハウツー記事もあわせてご覧ください。
バリアフリー住宅を検討されている方へ
住宅設計や高松スタジオでの相談も承っております。お気軽にご相談ください。







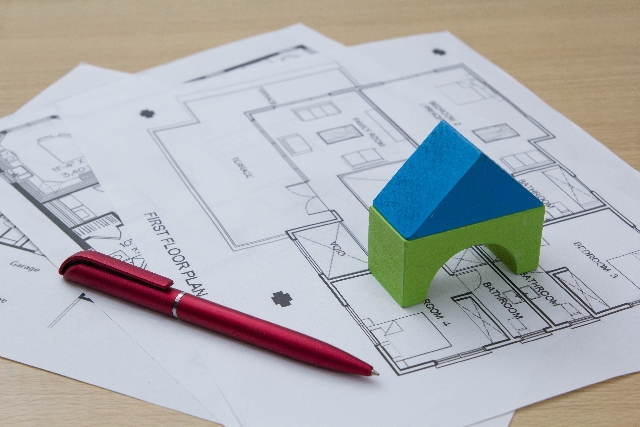

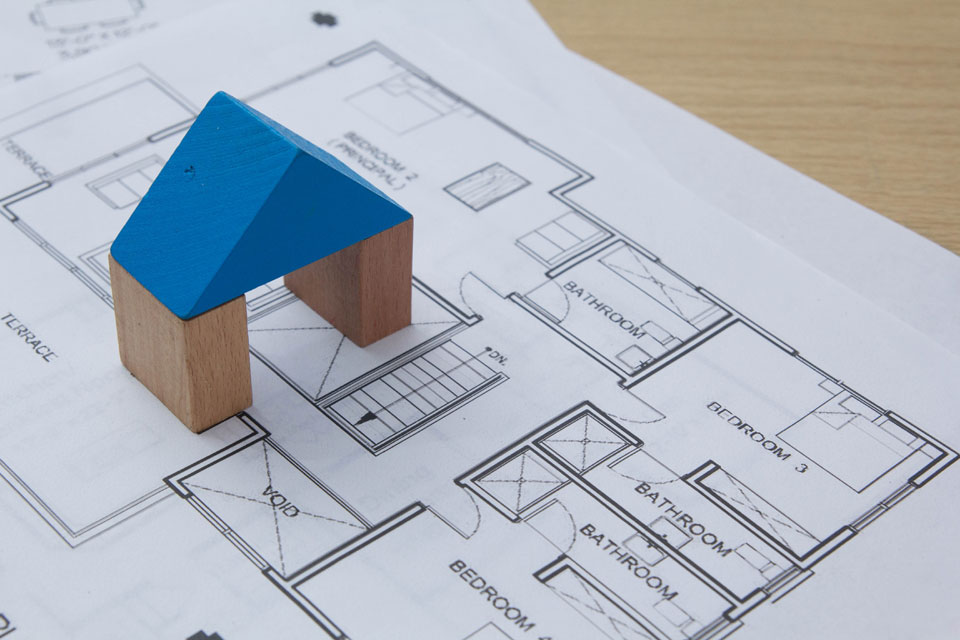

コメント